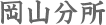JR山陽本線万富(まんとみ)駅から車で5分のところに「向山」という小高い山があります。ここにはかつて大本の中国別院がありました。(現在は向山公園として人々に親しまれています。)
この中国別院には王仁三郎が全国に建てた歌碑(48基)の一つがありました。いわゆる「向山歌碑」です。
|
|
 向山(中国別院があったところ) |
王仁三郎は霊的に重要な場所に歌碑を建てました。窪田英治氏によりますと、王仁三郎は48歌碑の建立後、こう言ったそうです。
そして、四十八の歌碑を建て終えると、自信をもって「日本の国は私が守ったんだ」といいました。「蟇目の法」で歌碑を建てたところと天柱を繋いだから、日本列島は沈まないのだと断言しているのです。(『予言と神話』 霊界物語研究会編 八幡書店)
向山歌碑について、当時の機関誌『真如の光』(昭和九年十二月十日号)はこう述べています。
なお、この歌碑は聖師様(註 出口王仁三郎のこと)より日本一の歌碑の御言葉をいただきたる立派なるもので、花崗岩にて高さ八尺、横巾十六尺、重量一千八百貫である。
この歌碑には王仁三郎が揮毫した歌15首が彫られています。
向山に中国別院が建設されるまでの大まかな流れは次のとおりです。
以下、中国別院の写真を掲載します。
 破却直前の中国別院と官憲(『大本七十年史』下巻より) (※画像をクリックすると拡大します)
 中国別院極楽橋渡初式(『壬申日記』より) (※画像をクリックすると拡大します)
なお、『出口王仁三郎と熊山』(あいぜん出版)にはこう書かれてあります。
中国別院「みろく館」は、緑の屋根であった。昭和十年事件で破壊されたわけだが、歌碑の残骸とともに、緑の瓦の破片がいまも向山山頂に点在している。
この資料集までに、写真を手配できなかったが、檜つくりの平屋。六一坪。白壁の土塀があり、周囲は五六間七寸の吉数。ご神体は聖師筆の「山越のみろく」であった。
上述の緑の瓦ですが、岡山の信者が愛善苑本部に献納しています。本部にご参拝の際にはぜひご覧になってみてください。
 |
| 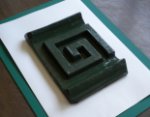 |
中国別院の屋根瓦
(※画像をクリックすると拡大します) |
余談ですが、向山のすぐ近くには東大寺瓦窯(かわらがま)跡(鎌倉時代初期に東大寺再建のために瓦を焼いた窯の跡)があります。
 国史跡 万富(まんとみ)東大寺瓦窯(かわらがま)跡 (※画像をクリックすると拡大します)
|